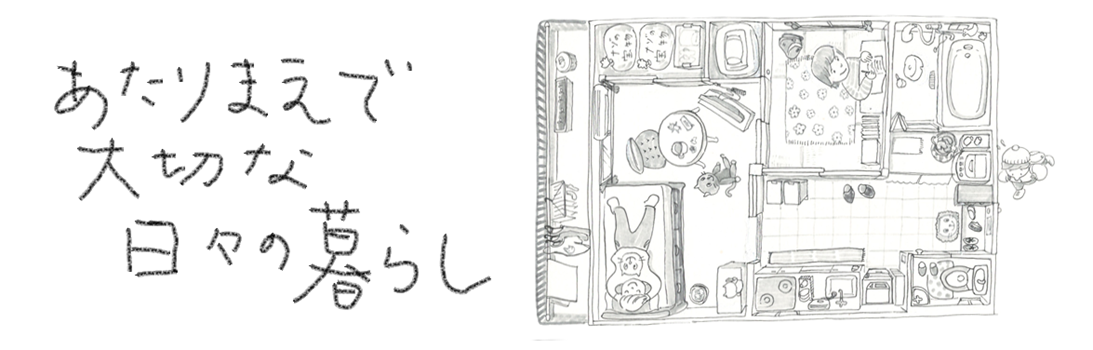ヒビノクラシ富士見台カフェでは、毎週土曜日の12時から17時まで、食堂「土曜日のスプーン」をやっています。野菜を中心としたご飯、甘さ控え目のデザート、ドリンク、すべてスタッフが手作りする、美味しくて体に優しい料理をご用意しています。ドネーション制(自由料金制)なので、お金のある人も、そうでない人も、同じ料理を同じだけ召し上がっていただけます。
食堂のスタッフは普段、地域でアパートを借りて暮らす知的障害のある人の暮らしを支える、ヘルパーの仕事をしています。そんなことから、子どもを連れたママ友グループや、ご近所の人、カフェ巡りが趣味のお客さんに交じって、障害のある人も居合わすことがよくあります。様々な背景を持つ人たちが、偶然にも、同じ空間で同じ時間を共にするわけですから、ハプニングはつきものです。この、ハプニングの遭遇とそれを楽しめるやりとりこそが、他の食堂では決して味わえないであろう、土曜日のスプーンの「もうひとつの美味しさ」だと思っています。
社会を見渡すと、「障害のある人の存在が全く想定されていないお店」か、逆に「計画的に障害のある人だけを集めたお店」か、さもなくば「特定のイデオロギーの信奉者とそれに親和するマイノリティだけが居心地のいいお店」か、そのいづれかだということに気がつきます。もちろん私は、それらお店の社会的存在意義を否定したいわけではありません。実際、素晴らしい取り組みをしているお店があることも、そんなお店に救われている人がいることも、知っています。ただ、私たち自身が営むお店として考えたとき、それら既存のお店とは別のものにしようと思ったのです。
インクルージョンやダイバシティという言葉が一般化するにつれて、社会は――それがコスパに象徴される経済効率性からであれ、功利主義的な価値観からであれ、ヘイトクライムに対抗する善意からであれ――人々から「偶然の出会い」を奪ってしまっているように思うのです。その結果、社会には自分(と仲間達)とは異なる他者が存在するという、当たり前のことに思いが及びにくくなり、ハプニングに遭遇する機会も、それを楽しむ心の余裕さえも、奪われてしまっているように思えてなりません。ハプニングの種は、「同質化が企図された計画的な出会い」の中へと押し込まれ、計画を推進する専門職の管理によって発芽を抑え込まれます。管理の網の目を潜り抜けて芽を出せば、直ちにトラブルと呼び変えられ、摘み取られてしまうのです。
そもそも富士見台カフェは、支援の専門職に就く私たち自身が、知的障がいのある人たちと出会い直したいと思って始めました。自立生活支援の仕事では、「ヘルパー/利用者」として出会うしかなく、「支援する人/される人が固定化された関係性」のままつき合い続けていくほかにないのです。その出会いと経験も、かけがえのないものではあるのですが、それとは別の出会いから始まる、別の関係性にもとづいたつき合いも、してみたいと思ったのです。すれば、両者の関係に変化は生じるのか?小さな社会空間としてのカフェに何かが生まれるのか?そこでのケアはどのように立ち現れるのか?そもそもケアとは?支援とは?コミュニティとは? いろいろ確かめてみたいと思ったのです。
(富士見台カフェ通信・二〇二四年 春号 より)